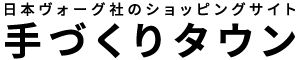山口怜子さん
 1944年大分県大山町に生まれる。1966年福岡県三井郡北野町の天保年間から続く造り酒屋に嫁ぐ。1970年古布を使って、刺し子風の継ぎ合わせを始めるが、独自の尺貫法を用いる。1980年「藍公房」を主宰。1982年アメリカのナショナル・キルト連盟レディバグ主催のキルト大会に招待され、6点を紹介。全作品が入賞、内3点がブルーリボン賞を受賞。ワシントンDCで開かれた駐米大使主催の日米協会レセプションに招待出展。2000~01年日本巡回展(主催・朝日新聞社)。「藍公房」を「矢口玲子デザイン室」に改称。著書に『花裂あわせ』(日本ヴォーグ社刊)、『21世紀へ語り継ぐ山口怜子の世界』(朝日新聞社)など。
1944年大分県大山町に生まれる。1966年福岡県三井郡北野町の天保年間から続く造り酒屋に嫁ぐ。1970年古布を使って、刺し子風の継ぎ合わせを始めるが、独自の尺貫法を用いる。1980年「藍公房」を主宰。1982年アメリカのナショナル・キルト連盟レディバグ主催のキルト大会に招待され、6点を紹介。全作品が入賞、内3点がブルーリボン賞を受賞。ワシントンDCで開かれた駐米大使主催の日米協会レセプションに招待出展。2000~01年日本巡回展(主催・朝日新聞社)。「藍公房」を「矢口玲子デザイン室」に改称。著書に『花裂あわせ』(日本ヴォーグ社刊)、『21世紀へ語り継ぐ山口怜子の世界』(朝日新聞社)など。
山口怜子さんが、この江戸天保年創業の老舗、庭の鶯酒造に嫁いでいできたのは、21歳の時。「お嬢様のように何もしなくていい」という最初の口上は、家の中の切り盛り、育児、接客など現実の暮らしの前では吹き飛んだ。江戸時代の建物という造り酒屋の家屋には、時代の埃が積もった黒く太い梁がくすみ、二階は古い箪笥や長持ちなど、道具類で埋まっていた。そんな家を片付けていた中で見つけたのが、ひとつの小さな柳行李。中には、この家に仕えた女性たちがお針仕事の稽古で使ったものだろうか、傷んだところを細かい針目で繕った布などが、丁寧にたたんで入っていた。「そのボロと言ってもいいような布に、心を揺さぶられたのです。特にちくちくと繕った針目のひと針ひと針に、こうしてものを大事にしながら暮らしてきた人たちの質素でありながら豊かな心を感じ、全部使って残そうと思いました」ここに山口さんのパッチワークの原点がある。どんなに汚れ、傷んでいても、それぞれの布には人の思い出があり、歴史がある。それを我が家の次の世代に残しておきたいという願いが、つぎ接ぎになった。
どこの家にも捨てきれず押し入れにしまってある洋服や布類がある。それらは歳月とともに汚れたり傷んだりしているが、まさしく日本の家族の歴史を染み込ませた布である。ひたすら捨てられたり燃やされたりするのを待っていた布たちに新たな息吹を吹き込み、文字通り我が家だけのかけがえのない宝物として残す。山口さんのキルトの立脚点はここにある。「先生は『買った布は持ってこないでね、思い出がないからデザインが難しいの。家で着古した洋服を持ってきて』としつこく言われます。そして、布にまつわる話を聞かせてと。みんなが思い出を語ってくれることがすでにデザインの半分を担っているのよと」と助手の立木さんが話す。そしてもうひとつ、山口さんがこだわるのが、日本古来の規矩法による採寸である。古来日本の神社仏閣を建てた計算単位は、着物にも用いられており、その布を使い切り、日本建築との調和を求めれば、必然的に規矩法に拠るべきというのが、山口さんの考えなのだ。そこで最初、宮大工の人に規矩法の出し方を習って、独自のパターンを作っていた。「私のキルトは、日本の規矩法によるものです。私にとってとても重要なことなのです。これを少しでも次の世代に伝えることができれば嬉しいです」
─本文より一部抜粋─ キルトジャパン2004年1月号より
 『山桜(さんおう)』1974~1981年制作 260×230cm 山口怜子デザイン室所有
『山桜(さんおう)』1974~1981年制作 260×230cm 山口怜子デザイン室所有
1982年米トラディショナルキルト連盟LADY BUG主催大会 ブルーリボン賞受賞作品
春、小学校へ通う道すがら見た、雨に煙る山にポツンと一本の山桜山口さんはその自然の光景を今だ忘れることはない。グレーの布は昭和28年の大水害で白の絹布団が泥で染まったもので、ピンク系の布は着物の裏地の紅絹。最初はスカート、次にこどもたちの布団、そして故郷大山町の美しい山桜の作品に作り変わっていった。記念すべき大作の第1作目。 『生命のダンス』1988年制作 220×110cm 山口怜子デザイン室所有
『生命のダンス』1988年制作 220×110cm 山口怜子デザイン室所有
ピーマン、魚、空想の動物などを生命にたとえ、広大な宇宙で楽しく踊っている様子を明るい色彩の帯の裏地を使って表現している。キルト綿の代わりに、こどもたちのおむつや、義姉たちの寝巻も使われている。 『貞一(さだいち)』2002年制作 160×120cm 所有・製縫者/帖池淳子
『貞一(さだいち)』2002年制作 160×120cm 所有・製縫者/帖池淳子
赤と白の華やかな花を咲かせたキルトは、親愛なる祖父の名前がつけられている。布は祖父のモーニングのズボンと戦争時代に着用したコート、そして祖母の着物裏地の3点が使われている。二度度起こしたくない、辛い戦争のさなか、どんな思い出があったのだろう。 着古したシャツやブラウス、スカート、コートなど様々な衣類が詰まった段ボールが宅配便で届けられる。布にまつわる思い出話を聞き、キルトのデザインを起こすのが唯一の楽しみだ。
着古したシャツやブラウス、スカート、コートなど様々な衣類が詰まった段ボールが宅配便で届けられる。布にまつわる思い出話を聞き、キルトのデザインを起こすのが唯一の楽しみだ。